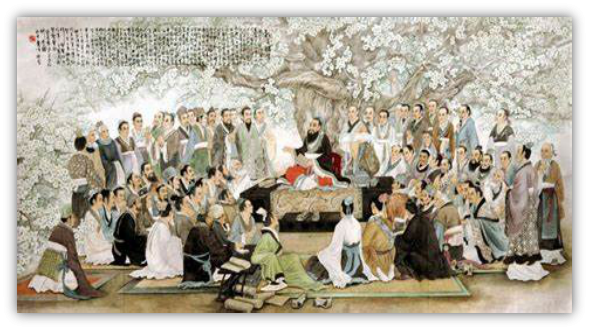伝
漢文
有子曰、信近於義、言可復也。
書き下し文
有子曰く、信 は義 に近ければ、言 は復 む可きなり。
集解
漢文
復、猶覆也。義不必信、信非義也。以其言可反覆、故曰近義。
書き下し文
復は猶ほ覆のごときなり。義 は必ずしも信 ならず、信 は義 に非ざるなり。以ちて其の言 の反り覆 む可きなるは、故に義 に近きと曰ふ。
現代語訳
『復』とは『覆』の類語である。『義』とは必ずしも『信』ではなく、『信』は『義』ではない。その言葉のうち履行すべきことについては、つまり「義に近い」というのだ。
伝
漢文
恭近於禮、遠恥辱也。
書き下し文
恭しきも禮に近かれば、恥辱 を遠ざくなり。
集解
漢文
恭不合禮、非禮也。以其能遠恥辱、故曰近禮也。
書き下し文
恭しくも禮に合はざれば、禮に非ざるなり。其の能く恥辱 を遠ざくを以ちて、故に禮に近かればと曰ふなり。
現代語訳
恭順であっても礼に合致しないなら非礼である。そのうち恥辱を遠ざけることができるものは、つまり「礼に近い」というのだ。
伝
漢文
因不失其親、亦可宗也。
書き下し文
因 しみて其の親しきを失はざれば、亦た宗と可きなり。
集解
漢文
孔曰、因、親也。言所親不失其親、亦可宗敬。
書き下し文
孔曰く、因は親なり。親しむ所は其の親を失はざるは、亦た宗敬 ぶ可きと言ふ。
現代語訳
孔氏はいう。『因』とは『親』である。親しい者がその親愛を失わないことこそ、大いに崇敬すべきことであると言っているのだ。
疏 有子曰至宗也
漢文
疏有子曰至宗也。
○正義曰、此章明信與義、恭與禮不同、及人行可宗之事。信近於義、言可復也者、復猶覆也。人言不欺為信、於事合宜為義。若為義事、不必守信、而信亦有非義者也。言雖非義、以其言可反復不欺、故曰近義。恭近於禮、遠恥辱也者、恭惟卑巽、禮貴會時、若巽在牀下是恭、不合禮則非禮也。恭雖非禮、以其能遠恥辱、故曰近禮。因不失其親、亦可宗也者、因、親也。所親不失其親、言義之與比也。既能親仁比義、不有所失、則有知人之鑒、故可宗敬也。言亦者、人之善行可宗敬者非一、於其善行可宗之中、此為一行耳、故云亦也。
書き下し文
疏 有子曰至 宗也。
○正しき義 に曰く、此の章 は信と義、恭と禮の同じからざる、及び人の行 の宗 ぶ可きが事を明らむ。信 は義 に近ければ、言 は復 む可きなり者 、復は猶ほ覆のごときなり。人の言ひて欺かざるは信 と為し、事に於いて宜しきに合ふは義 と為す。若し義の事を為さば、必ずしも信 を守らず、而るに信 も亦た義 に非ざる者有るなり。言 は義 に非ざると雖も、以ちて其の言 の反復 みて欺かざる可きは、故に義に近しと曰ふ。恭しきも禮に近かれば、恥辱 を遠ざくなり者 、恭しきは惟 ふに卑巽 たり、禮は時に會ふを貴 び、巽 ること牀 の下に在るが若きは、是れ恭しくも禮に合はず、則ち禮に非ざるなり。恭しきは禮に非ざると雖も、其の能く恥辱を遠ざくを以ちて、故に禮に近しと曰ふ。因 しみて其の親しきを失はざれば、亦た宗と可きなりと者 、因は親なり。親しまるる所の其の親しむを失はざるは、義 の之れ與に比 ふを言ふなり。既に能く仁に親しみ義 に比 ひ、失はるる所有るにあらざれば、則ち知人の鑒 を有 てり、故に宗敬 ふ可きなり。亦と言ふ者、人の善き行 の宗敬 ふ可き者は一つに非ず、其の善き行 に於いて宗 ぶ可きの中、此の為すは一 の行 のみ、故に亦と云ふなり。
現代語訳
○正義(正統な釈義)は次の通りである。
この章は「信と義、恭と礼が同一ではないこと」「人の行いのうち崇敬すべきこと」について明らかにしている。
「信 は義 に近ければ、言 は復 む可きなり」とはどういうことか。『復』とは『覆』の類語である。人が発言して欺かないことが『信』であり、事の適宜に合致することが『義』である。もし『義』を為すのであれば、必ずしも『信』を守らないし、『信』も同様に『義』ではないものがあるのだ。言葉が義ではないとしても、その言葉を履行して欺いてはならないものであれば、つまり「義に近い」という。
「恭しきも禮に近かれば、恥辱 を遠ざくなり」とはどういうことか。『恭』とは『卑巽』のことであろう。礼とは時機に適うことが大切であり、『へりくだってベッドの下に潜り込む』というような事態は、確かに恭順ではあるものの礼には合致せず、つまりは非礼なのだ。恭順が礼に合致しない場合でも、それが恥辱を遠ざけることのできるものであれば、つまり「礼に近い」という。
「因 しみて其の親しきを失はざれば、亦た宗と可きなり」とはどういうことか。『因』とは『親』である。親しい者がその親愛を失わないのが義に従うことなのだと言っている。既によく仁に親しみ義に従い、過失を有さないのであれば、『知人の鑒 』を有している。だから大いに崇敬すべきなのだ。『亦』と言葉にしているのは、崇敬すべき人の善行はひとつではないが、それら崇敬すべき善行のうち行うのはひとつだけであるから『亦』というのだ。
疏 義不必信、信非義也
漢文
○注義不必信、信非義也。
○正義曰、云、義不必信者、若春秋晉士匄帥師侵齊、聞齊侯卒、乃還。春秋善之。是合宜不必守信也。云信非義也者、史記尾生與女子期於梁下、女子不來、水至不去、抱柱而死。是雖守信而非義也。
書き下し文
○注義不必信、信非義也。
○正しき義 に曰く、義は必ずしも信 ならずと云ふ者 、春秋に晉の士匄の師 を帥 ゐて齊を侵すも、齊の侯 の卒 を聞き、乃ち還るが若 し。春秋は之れを善しとす。是れ宜しきに合ひて必ずしも信を守らざることなり。信 は義 に非ざる也と云ふ者、史記に尾生と女子 の梁 の下に期 するも、女子 は來たらず、水は至るも去らず、柱を抱へて死せり。是れ信 を守ると雖も而りて義 に非ざるなり。
現代語訳
○正義(正統な釈義)は次のとおりである。
「『義』とは必ずしも『信』ではない」とはどういうことか。春秋に、晋の士匄が軍隊を統帥して斉に侵攻したが、斉侯が卒去したと聞き、そのまま引き返したとあるのがそれだ。これを春秋は善だとした。これぞ適宜に合致して必ずしも信を守らないことなのだ。
「『信』は『義』ではない」とはどういうことか。史記によれば、尾生は女子と橋の下で会う約束をしていた。女子は来ないので水位が限界に達しても立ち去らず、柱を抱えたまま死んだという。これぞ信を守りながらも義に合致しないものである。